
沿革
薬用植物資源研究センター北海道研究部は、昭和39年、北方系薬用植物の試験栽培研究を目的に国立衛生試験所北海道薬用植物栽培試験場として設置された。組織は、栽培管理室、庶務係、 圃場作業室で発足した。現在は栽培研究室が置かれている。所在地は、旭川市の北約80km、名寄盆地の北部、天塩川と名寄川の合流点付に位置し、年平均気温5.5度、平均積雪113.2cmの道内屈指の寒冷豪雪地帯である。
北海道は、薬用植物の栽培が盛んであり、漢方薬あるいは製薬原料に利用される重要生薬の生産地である。北海道研究部は、寒冷地に適する薬用植物の栽培技術に 関する研究、調製方法の改良および開発に関する研究、優良品種の選抜・育成に関する研究、薬用植物資源の保存に関する研究などを行っている。
| 位置: | 北緯 44°22′ | 東経 142°28′ |
| | 標高 98 m |
| 気温: | 平均気温 6.3゜C |
| | 最高気温 32.8゜C |
| | 最低気温 -23.0゜C |

寒冷地における薬用植物の栽培研究
寒冷地に適した薬用植物について、安定した収量と均一な品質を確保するために、種子の発芽特性と播種期、栽植様式、無機成分の吸収過程と施肥法、収穫期と有
効成分との関係、調製方法などの試験研究を行っている。また、輸入あるいは野生植物の採取に依存している植物については新規に導入し、国内での栽培化を目指し
た研究を実施している。現在、栽培研究を行っている主な植物は以下の通りである。
カンゾウ、ゲンチアナ、モッコウ、オウギ類、ウイキョウ、ケシ、ムラサキ、サイシン類、ヨロイグサ。

優良品種の選抜・育成の研究
生薬が医薬品としての品質を一定に保つために、基原となる薬用植物の品種育成に取り組んでいる。シャクヤク、トウキ、ナイモウオウギ、ホソバオケラ、ダイオウ、
ハトムギに関して、成分組成、性状、多収性、環境耐性、早熟性などについて試験研究を行っている。
北海道研究部ではシャクヤクにおいて安定して収量が高く、paeoniflorin含量の高い品種「北宰相」を育成(1996年品種登録)し、ハトムギでは早生で種子の熟期
が早く、北海道においても栽培可能な「北のはと」を育成(現在品種登録中)した。

薬用植物資源の保存
標本園・薬木園では寒冷地に適した薬用植物・薬木が約500種類植栽されており、ハーブ類も多く含まれている。アイヌ民族の有用植物園では、アイヌ民族が利用し
ていた有用植物を約120種類植栽している。世界的に伝統医療が再評価される中で、薬用植物と生薬の正しい知識の普及を図るほか、研究材料の提供、優良遺伝子の保
存、生態研究などに利用されている。
交通案内
JR宗谷本線,名寄駅下車 タクシーで10分(約4km)
旭川空港より車で約1時間40分(約80km)
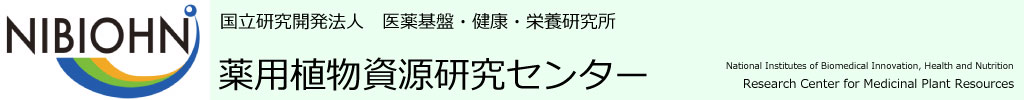

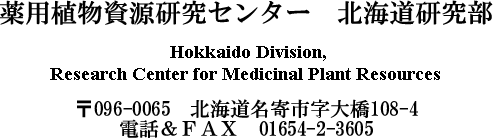


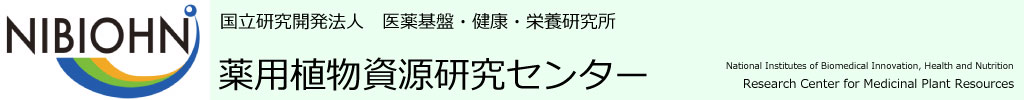

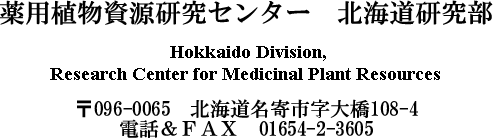


 沿革
沿革 寒冷地における薬用植物の栽培研究
寒冷地における薬用植物の栽培研究








 優良品種の選抜・育成の研究
優良品種の選抜・育成の研究




 薬用植物資源の保存
薬用植物資源の保存